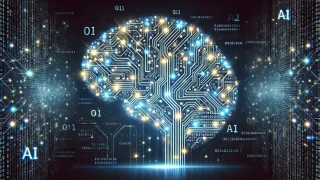【徹底解説】新リース会計の影響&簡単チェックリスト付き!

ここ数年、会計基準の変更が続き、経理・財務部門の皆さんも「また新しいルールが…」と感じることが多いのではないでしょうか。そんな中でも、2027年4月から適用される新リース会計基準は、特に注目すべき改正です。従来のリースの扱いが大きく変わり、企業の財務報告や経理実務に少なからぬ影響を与えることが予想されています。
これまでオフバランスで済んでいた多くのリース契約がオンバランス化されることで、財務指標に変化が出るだけでなく、契約書の見直しや仕訳処理の工数増加など、経理部門の負担が増える点が大きな課題です。一方で、正しく準備を進めることで、こうした負担を効率的に軽減することも可能です。
本記事では、新リース会計基準がどのような内容で、どんな影響があるのかを分かりやすく解説します。さらに、対応をスムーズに進めるためのシステム選びのポイントや、新リース会計に対応しているオススメのシステム「TOKIUM契約管理」、「固定資産奉行V ERPクラウド」、「ProPlus+」をご紹介します!
資料ダウンロード(無料)
目次
目次(クリックでジャンプします)
そもそもリース会計とは?

リース会計とは、企業がリース取引を通じて利用する資産や設備に関して、その取引内容を財務諸表に適切に反映するための会計ルールのことです。リース取引は、企業が必要な資産を直接購入するのではなく、リース会社から一定期間借りる形で使用する契約であり、初期投資を抑えながら資産を活用できる点で広く利用されています。
従来のリース会計では、リース取引を以下の2つに分類して処理してきました。
- ファイナンスリース
資産を購入するのに近い性質を持つリースであり、貸借対照表に資産と負債を計上します。このリースでは、契約終了後に資産の所有権が移転する場合もあります。 - オペレーティングリース
賃貸借に近い形態のリースであり、貸借対照表には計上せず、リース料を費用として損益計算書に記載します。比較的短期間の契約が一般的です。
リース会計の目的は、企業の財務情報を正確に示すことにあります。リース取引は資産や負債に直接関わるため、その会計処理が適切に行われることで、企業の経営状況が透明に表現され、投資家や利害関係者からの信頼を得ることができます。
新リース会計基準

「新リース」とは、現行のリース会計基準を見直し、2027年4月から適用される新しいリース会計基準を指します。新基準では、従来のリース会計ルールにおける「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」の区分が廃止され、リースの大部分が貸借対照表に計上されるようになります。
適用開始時期
- 2027年4月1日以降に始まる会計年度から適用(強制)
- 早期適用は2025年4月1日から可能(任意)
具体例:
- 3月決算の企業 → 2028年3月期から適用
- 6月決算の企業 → 2028年6月期から適用
- 12月決算の企業 → 2028年12月期から適用
自社の決算期をチェックし、準備を進めましょう!
背景
リース会計が現在注目されている背景には、新しいリース会計基準の導入が大きく影響しています。この基準改正は、リース取引に関する財務報告の透明性を高め、国際基準との整合性を図ることを目的としています。しかし、基準の変更に伴い、企業の財務諸表や経理業務、さらには経営指標に大きな影響を与えることから、多くの企業にとって対応が避けられない重要な課題となっています。
1. 国際基準への対応が求められている
新しいリース会計基準は、国際会計基準(IFRS 16)に準じたルールへ変更されます。従来の日本基準では、「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」に分類され、後者については貸借対照表(バランスシート)への計上が不要とされていました。しかし、新基準では、この区分が廃止され、原則すべてのリース契約を貸借対照表に計上することが求められるようになります。
この改正により、企業の財務状況がより正確に反映され、投資家や取引先からの信頼性が向上すると期待されています。一方で、会計処理の複雑化や経理業務の負担増加といった課題が生まれることも事実です。
2. 財務諸表への大きな影響
新基準に基づくリースのオンバランス化は、以下のような財務諸表への影響を伴います。
- 資産と負債の増加
貸借対照表に「使用権資産」と「リース負債」が計上されるため、企業の総資産と総負債が膨らみます。これにより、自己資本比率やROA(総資産利益率)などの経営指標が変化する可能性があります。 - 費用計上の早期化
従来のリース料計上から、減価償却費と利息費用に分かれる形で費用が計上されるため、費用が初期に集中しやすくなる傾向があります。これにより、企業の利益構造にも影響を与える可能性があります。
3. 実務面での課題と負担増加
新リース会計基準への対応には、企業の実務にも多大な影響があります。特に以下の点が挙げられます。
- 契約の洗い出しと判定作業
企業はすべての契約を精査し、新基準に基づきリース該当性を判定する必要があります。これには、賃貸借契約や業務委託契約など、これまでリースとみなされていなかった契約も含まれるため、膨大な作業量が想定されます。 - 仕訳処理の増加
オンバランス化によってリースに関連する仕訳が大幅に増加するため、経理部門の負担が大きくなります。一部の企業では、仕訳のボリュームが3倍から5倍になるとも言われています。 - システムや業務プロセスの見直し
既存の会計システムや契約管理方法が新基準に対応していない場合、システムの更新や業務プロセスの再構築が必要となります。
4. 適用開始時期と早期対応の必要性
新リース会計基準の適用は、2027年4月1日以降に開始する事業年度から強制されます。ただし、2025年4月1日以降に開始する事業年度からの早期適用も可能です。この基準変更により、企業は契約管理の見直しや会計処理の準備を進める必要があります。
基準の適用には時間とコストがかかるため、早期に対応を始めることで、実務負担を分散し、準備不足によるリスクを軽減することが重要です。
主な変更点
新リース会計基準では、これまでのリースの扱いが大きく変わります。特に重要な変更点を、分かりやすくまとめました。
1. ほぼ全てのリースがオンバランス化
従来は「オペレーティングリース」(賃貸借契約に近いリース)は貸借対照表に計上しませんでしたが、新基準では原則すべてのリース契約を資産と負債として計上する必要があります。これにより、企業の財務諸表に大きな変化が生じます。
2. リースの範囲が広がる
新基準では、リースの定義が見直され、これまで対象外だった不動産賃貸借契約や業務委託契約などもリースに該当する可能性があります。そのため、契約内容の詳細な確認が求められます。
3. 会計と税務の処理が異なる
新基準ではリース契約をオンバランス化しますが、税務上は従来どおり「オペレーティングリースはオフバランス」のままです。この違いによって、税務申告の際に調整作業が必要となり、経理業務の負担が増える可能性があります。
どんな企業が対応を求められるのか?
新リース会計基準は、すべての企業に適用されるわけではありません。主に日本会計基準(JGAAP)を適用している企業が対象となり、特に以下の企業に適用が求められます。
1. 上場企業およびその連結子会社
- 日本会計基準(JGAAP)を適用している上場企業が対象です。
- 金融商品取引法により、公正妥当と認められる企業会計基準(JGAAP)を適用することが義務付けられているため、新リース会計基準も適用されます。
- 新リース会計基準は「連結財務諸表」だけでなく、「個別財務諸表」にも適用が求められるため、連結子会社も新基準に対応する必要があります。
2. 未上場だが会社法上の大会社およびその連結子会社
- 会社法上の大会社:資本金が5億円以上、または負債総額が200億円以上の会社。
- 会社法上の大会社は、会計監査を受ける義務があるため、新基準の適用対象となります。
- 大会社の連結子会社も対象となるため、該当企業は事前に対応を進める必要があります。
☑自社が該当するか簡単チェック!
以下の条件に当てはまる企業は、新リース会計基準の適用対象です。
☑ 日本会計基準(JGAAP)を適用している
☑ 上場企業またはその連結子会社
☑ 未上場でも会社法上の大会社(資本金5億円以上 or 負債総額200億円以上)
☑ 大会社の連結子会社
すべて当てはまらない → 今回の基準適用は不要
1つでも該当 → 新リース会計基準に対応が必要!
新リース会計基準に対応するために企業がやるべきこと

新リース会計基準の適用に向けて、企業は早めに準備を進める必要があります。適用初年度の混乱を防ぐためにも、以下の 「4つのステップ」 を参考に、計画的に対応を進めましょう。
ステップ1:現状把握と影響額の試算
新リース会計基準では、ほぼすべてのリース契約がオンバランス化されます。そのため、まずは自社が持つリース契約の現状を正確に把握し、新基準が財務に与える影響を試算することが重要です。
〈主な対応ポイント〉
- 契約書の洗い出し
- 紙・電子を問わず、すべてのリース契約を確認
- 賃貸借契約や業務委託契約も含め、リース該当の可能性をチェック
- リース該当判定の実施
- 新基準の定義に照らし合わせ、どの契約が対象となるか判断
- 財務インパクトの試算
- 使用権資産 と リース負債 の計上額を計算
- 自己資本比率やROAへの影響を分析
意外な契約がリースに該当する可能性あり!
新基準では、店舗の賃貸契約や特定の業務委託契約もリースとみなされる可能性があるため、契約書の精査が必須です。
ステップ2:対応方針の検討
リース契約の見直しとともに、新基準に沿った会計処理や開示方法をどう管理するかを決定します。
また、経理部門だけでなく、財務、法務、購買、ITなど関係部署と連携し、企業全体で統一した対応方針を策定することが重要です。
〈主な対応ポイント〉
- 新しい会計処理ポリシーの策定
- 会計処理の変更内容を経理・財務部門で統一
- リース管理方法の統一
- 契約台帳や管理システムを活用し、リース情報を一元管理
- 関係部署との情報共有
- 法務、購買部門とも連携し、新基準に即した契約締結を推進
早めに社内で共通認識を持つことが重要!
新基準では、リース契約の判断基準が変わるため、関係部署と協力し、共通ルールを決めることが大切です。
ステップ3:業務設計とシステム導入
新基準に対応するには、会計処理の複雑化に備え、システムを活用した業務の効率化が必要です。
特に、契約管理の効率化やリース判定の自動化を進めるために、ITシステムの導入を検討する企業が増えています。
〈主な対応ポイント〉
- 契約管理システムの導入
- 契約書の電子管理・検索機能を活用
- AIによるリース該当判定で判断作業を効率化
- リース会計対応の自動化
- 使用権資産・リース負債の自動計算
- 仕訳の自動生成で業務負担を削減
- ERPや固定資産管理システムとの連携
- 既存の会計システムと統合し、スムーズなデータ管理を実現
手作業では対応が難しいため、システム導入が鍵!
契約の洗い出しやリース判定を手作業で行うのは非効率なため、リース会計対応システムの活用を検討しましょう。
ステップ4:運用開始とモニタリング
新基準適用後は、スムーズな運用と継続的な改善 が必要です。
リース契約の更新時には、適切な会計処理が行われているかを定期的にチェックし、システムや業務フローを最適化していきます。
〈主な対応ポイント〉
- 実際の運用開始
- システムを活用したリース管理・仕訳処理を開始
- 定期的なモニタリング
- システム運用状況の確認、リース契約の適正管理
- 会計監査への対応準備
- 必要に応じた業務改善
- システム設定の最適化
- 社内マニュアルや業務プロセスの改善
リース契約は更新が発生するため、継続的な管理が必須!
新基準に対応した仕組みを作り、定期的に見直しながら適切な運用を維持しましょう。
リース会計に対応しているシステムのメリット
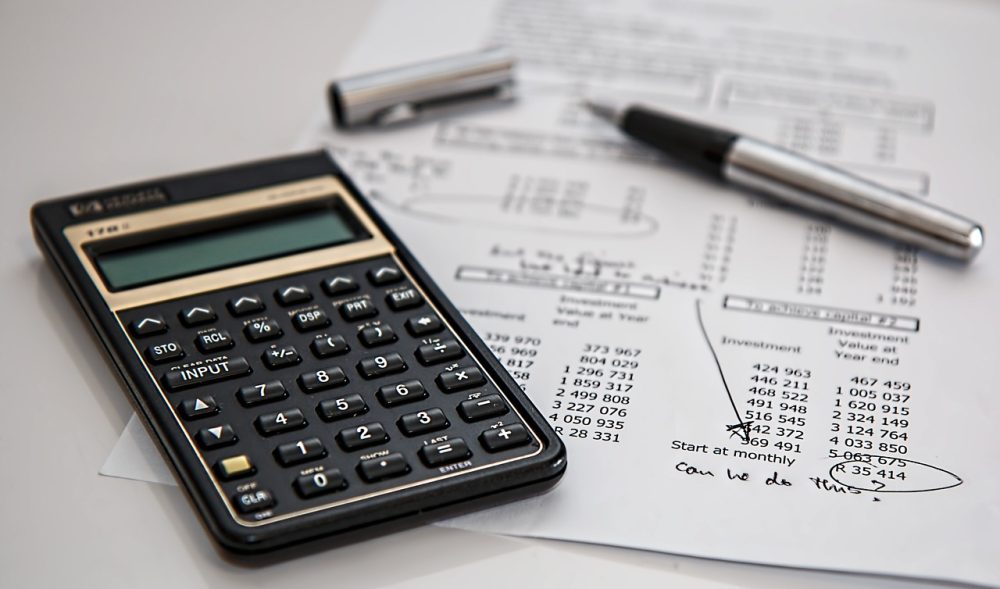
業務効率化
契約書の確認やリース該当判定、仕訳作成など、手作業では膨大な時間がかかる作業を自動化することで、工数を大幅に削減します。
人的ミスの削減
データ入力や仕訳の自動化により、転記ミスや計算ミスを防ぎます。これにより、経理部門の負担が軽減され、正確な財務データの作成が可能になります。
経営への貢献
正確かつタイムリーな財務データを提供することで、経営陣の意思決定をサポートします。新リース会計基準に基づく透明性の高い財務報告は、投資家や取引先からの信頼向上にもつながります。
システム導入前に検討すべきこと

新リース会計基準に対応するためにシステムを導入する場合、自社のニーズに合ったシステムを選ぶことが重要 です。
導入後に「思ったほど業務が改善されなかった…」とならないよう、事前に以下のポイントをしっかり検討しましょう。
① 導入目的の整理 「どの業務を改善したいのか?」を明確に!
システム導入の目的を明確にすることで、適切な機能を備えたツールを選定できます。自社の課題を洗い出し、どこに最も負担を感じているのか整理しましょう。
☑ 契約書の管理を効率化したい?
→ 契約書の一元管理、検索機能、電子契約との連携が必要
☑ リース該当判定を自動化したい?
→ AIによるリース該当判定、PDFデータの読み取り機能が重要
☑ 仕訳処理をスムーズにしたい?
→ 仕訳の自動生成機能、既存の会計システムとの連携が必要
☑ 財務報告や監査対応をスムーズにしたい?
→ 財務レポート作成機能、監査用データの出力が求められる
② システム選定のポイント 「どんなシステムを選べばいいのか?」
システム選定では、以下のポイントをチェックすることで、自社に最適なツールを選べます。
〈必須機能〉
リース会計対応システムにはさまざまな機能がありますが、「自社の業務に必要な機能があるか?」 を事前に確認しましょう。
☑ 契約書の一元管理・検索機能
☑ AIによるリース該当判定
☑ 使用権資産・リース負債の自動計算
☑ 仕訳の自動生成
☑ 財務レポート作成
☑ 既存のERP・会計システムとの連携
〈カスタマイズ性〉
システム導入後に、「このフォーマットでは業務に合わない…」とならないよう、
自社のワークフローに合わせてカスタマイズできるかも確認しましょう。
☑ レポートフォーマットを自由にカスタマイズできるか?
☑ 仕訳ルールを柔軟に設定できるか?
☑ 追加の項目(メモ欄、契約種別など)を登録できるか?
〈価格〉
システムの費用対効果を考え、「コストと機能のバランス」 を見極めることも大切です。
☑ 初期費用と月額費用の合計はいくらか?
☑ 追加ユーザーの課金体系は?
☑ 使わない機能に対して高額な費用を支払うことになっていないか?
〈サポート体制〉
リース会計システムは、導入後の運用やトラブル対応も重要。
しっかりサポートしてもらえるか確認しましょう!
☑ 使い方のトレーニングやFAQが充実しているか?
☑ 相談できるカスタマーサポートがあるか?
☑ 24時間対応 or 平日日中のみ?
③ 導入スケジュールの策定「いつまでに移行するのか?」
リース会計システムの導入には、契約・設定・データ移行・運用開始 というステップが必要です。
計画的に進めることで、スムーズな導入を実現できます。
新リース会計に対応できるシステム紹介
新リース会計基準に対応するには、契約管理やリース資産の会計処理を効率化できるシステムの導入が重要です。
ここでは、新リース会計対応のシステムとして「TOKIUM契約管理」、「固定資産奉行V ERPクラウド」、「ProPlus+」の3つのソリューションを紹介します。各システムの特徴や強みを比較し、自社に最適なツール選びの参考にしてください。
TOKIUM契約管理

サービス概要
TOKIUM契約管理は、紙および電子の契約書をクラウド上で一元管理するサービス。紙の契約書はTOKIUMが製本された状態のままスキャンし、データ化と保管も代行。AI-OCR技術により契約書の全文をデータ化し、取引先名や契約期間などの項目を自動で抽出。さらに、新リース会計基準に対応し、AIがリース該当契約を自動判定。リース資産管理の負担を軽減し、正確な会計処理をサポート。契約管理業務の効率化とガバナンス強化を実現する。
特徴
- リース該当の自動判定:AIが契約内容を分析し、リース該当の可能性を判定。該当部分をPDFにハイライト表示。
- 契約書のスキャン代行と保管:紙の契約書を郵送するだけで、スキャン・データ化・原本保管までを一括対応。
- AIによる契約情報の自動抽出:取引先名、契約期間、解約不能期間などをAIがデータ化し、手入力の負担を削減。
- 各種システムとのデータ連携:固定資産管理システムや店舗管理システムに直接インポートできるCSVデータを出力。
- 高セキュリティ体制:国内保管、秘密保持契約を締結したオペレーターが対応。ISMS認証・Pマーク取得済み。
※情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の第三者認証基準である国内規格「JIS Q 27001:2014(ISO/IEC 27001:2013)」の認証を取得済みです。(認証機関:SGSジャパン株式会社)認証登録番号:JP18/080504登録範囲:ソフトウェアの開発及び運用
料金
初期費用 + 基本利用料(1万円〜/月)+ 契約書の件数に基づく従量課金制
※詳細は要お問い合わせ
資料ダウンロード(無料)
固定資産奉行V ERPクラウド

サービス概要
固定資産奉行V ERPクラウドは、固定資産やリース資産の管理を一元化し、取得から除却・売却までのライフサイクルを網羅的にサポートするクラウド型システム。新リース会計基準にも対応しており、複雑な会計処理や仕訳データの作成を自動化。また、複数拠点でのデータ共有や会計システムとの連携により、生産性の向上と業務効率化を実現する。
特徴
- 固定資産・リース資産の一元管理:二重入力を排除し、資産情報を集中管理。
- 実務に即した詳細な管理:多様な資産のライフサイクルや償却方法に対応。
- データ共有と連携:複数拠点や税理士とのリアルタイムなデータ共有、会計・税務申告システムとの連携が可能。
- 高度なセキュリティ:データの暗号化、24時間365日の運用監視、国際認証SOC1・SOC2報告書の取得。
- クラウドの利便性:サーバー不要、プログラムの自動更新、自動バックアップによる運用負担の軽減。
料金
要お問い合わせ
ProPlus+
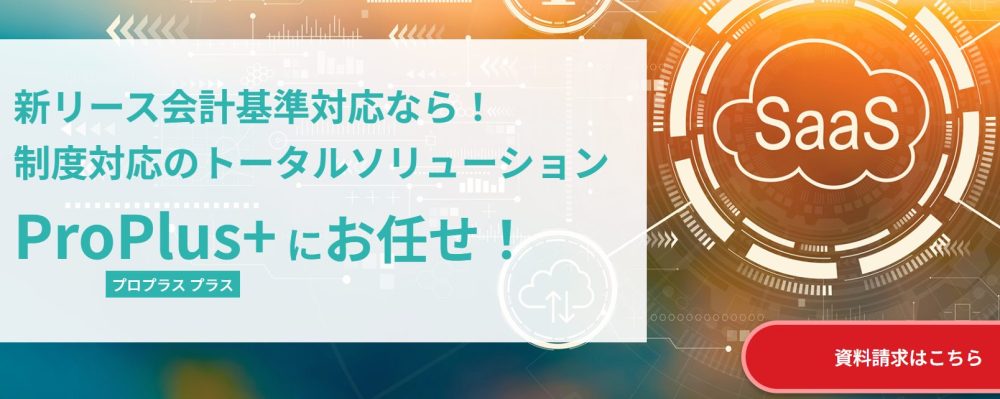
サービス概要
ProPlus+は、株式会社プロシップが提供する新リース会計基準対応のSaaSソリューション。約100社のIFRS16対応実績と、累計5,300社を超える資産管理ソリューションの導入ノウハウを活かし、リース契約のオンバランス処理やリース負債の見直しなど、リース管理業務全般を効率化する。
特徴
- 新リース会計基準対応:新リース会計基準以外にも、税務基準、IFRS16号など、複数の会計基準に対応した帳簿管理が可能。
- 自動判定機能:各契約をオンバランス・オフバランスに自動分類し、簡便的な処理(少額リース・短期リース)の判断も可能。
- リース負債の見直し:リース料や期間の変更に伴うリース債務の再計算処理に対応。
- 開示情報対応:使用権資産・リース負債の開示情報や、リース債務の返済予定表の出力が可能。
- 仕訳出力機能:契約の新規、変更、満了に至るまでの各増減の仕訳データを出力。
料金
要お問い合わせ
資料請求はこちら
まとめ
新リース会計基準の導入によって、これまでオフバランスだったリース契約の多くがオンバランス処理になり、企業の財務や経理業務に影響を与えることになります。「うちの会社も対応が必要?」と気になった方は、まず適用対象かどうかをチェックし、どんな準備が必要なのか整理することが大切です。
特に、契約書の管理やリース該当の判定、仕訳作成の手間が増えるため、手作業での対応には限界があります。そこで、リース会計対応のシステムを活用することで、業務の負担を軽減し、正確な会計処理が可能になります。
今回紹介した「TOKIUM契約管理」、「固定資産奉行V ERPクラウド」、「ProPlus+」は、それぞれ異なる強みを持ち、新リース会計に対応した便利な機能を備えています。自社に合ったシステムを導入すれば、経理業務がぐっと楽になり、スムーズな運用が実現できます。
2027年の適用開始まで、まだ時間はありますが、準備は早いほど安心! まずは、自社のリース契約を洗い出し、どんな対策が必要かを考えるところから始めましょう。今からしっかり準備を進めて、新リース会計基準にスムーズに対応していきましょう!